シャンソンという音楽
「シャンソン(chanson)」という言葉をご存じだろうか。
フランス語で歌全般を示す語句だが、日本では、フランスのすべてのジャンルの歌ではなく、近代のポピュラー・ソング、つまり日本の流行歌、歌謡曲に相当する歌だけをシャンソンと呼んでいる1)。
このシャンソンが日本中を席巻したのが、昭和20年代後期から30年代前半であった。芦野宏、高英男、中原美紗緖、越路吹雪、岸洋子など人気歌手が次々に登場して、リサイタルは満員が続いた。今では想像できないが、新発売の海外歌手のレコードについて、評論家がその背景を解説し、聴衆のもとレコードをかけて聴くというスタイルのコンサートが成立し、それも満員であった。
都心部では「シャンソン喫茶」と呼ばれる喫茶店が次々に生まれた。そこではレコードを流したり、歌手の生歌を聴かせたりして、店によっては歌手希望の人たちにレッスンをすることもあった。それら喫茶店はシャンソン好きな若者が集まり、銀座にあった「銀巴里」では、なかにし礼(後に作詞家・小説家)がウエイターとして働き、丸山明宏(後の美輪明宏)はここから歌手人生をスタートさせた。
ラジオでは『シャンソン・アワー』(昭和31年~ニッポン放送)、テレビでは『シャンソン・アルバム』(昭和30年~NHK)といった「シャンソン」を冠した番組も放送され1)、この頃、ラジオの音楽番組ではシャンソンが全体の25~30%を占めたという2)。
レコードの人気やコンサートの盛況も含めて、これらの現象は「シャンソン・ブーム」と呼ばれた。日本が豊かになるにつれて、さらに海外から多くの音楽が輸入されるようになり、その趣味嗜好の多様化などにより、昭和30年代中頃にはブームは早々にピークを過ぎてしまったが、現在も愛好者は多く、シャンソン歌手のためのコンクールも開催されている(KCAシャンソンコンクール、日本シャンソンコンクールなど)。
その「シャンソン」であるが、日本での事の始まりが宝塚少女歌劇(現在の宝塚歌劇)であることはあまり知られていない。当時、大阪から離れたさびれた温泉しかなかった宝塚という土地に余興として生まれた宝塚少女歌劇に、阪急電鉄の創始者である小林一三は大きな可能性を見出していた。大正年間から演出家を外遊させて、最先端の演劇のエッセンスを導入し、そこから日本初のレビュー『モン・パリ』(岸田辰彌演出)や後に続く、『パリゼット』『ローズ・パリ』『花詩集』(白井鐵造演出)など、「第一期レビュー黄金期」と呼ばれるレビューの名作が次々に生み出された。
それらレビューにはフランスから持ち帰った楽曲が使用された。『モン・パリ』は岸田がパリのパラース座で見たレビュー『パリ・ヴォワイユール』が基になっているが、その主題歌に日本語の詞を付けて『モン・パリ』にも使用された。『パリゼット』の主題歌は、オリジナルはドイツの曲であったがフランスで『白いリラが咲くとき』というタイトルで多くの歌手に歌われていた。それに白井も日本語詞を付けて『すみれの花咲く頃』というタイトルに変えて『パリゼット』の主題歌とした。天津乙女が歌ったこの曲は大ヒットして、現在も宝塚歌劇ではイベントや節目に代表歌としてよく用いられている。他にも同演目では『パリゼット』『おお宝塚』『モンパルナス』『ラモナ』『君の手のみマダム』『恋、あやしきは恋』が使用されて、いずれも白井がフランスから持ち帰り、作品にあったメロディーに日本語詞を付けたものである1)。
宝塚少女歌劇から始まり、トーキーのフランス映画が輸入されてその主題歌に触れる中で、日本人がシャンソンを知る機会が増えていった。戦時中に、音楽も軍国主義一色となり、一時期その交流は途絶えるが、昭和20年代後半のブームから再びシャンソンは日本に広がり、現在も多くの人々に親しまれている。
深緑夏代の歌手人生~宝塚歌劇時代

深緑夏代(本名:多田玲子)はその宝塚少女歌劇団(注1)の出身である。
大正10年(1921)、日本統治下にあった京城に生まれ、祖父母の在所である対馬の女学校に入学したが、一学年修了後の昭和10年(1935)に宝塚音楽歌劇学校に入学している。初舞台は翌年11月の大劇場星組公演の『バービィの結婚』で、当初は深緑夏子という芸名であった(昭和29年に夏代に変更)。
もともとはオペラ歌手希望で、東京音楽学校(後の東京芸大音楽部)志望であったが、本人が雑誌に書いたところによると「経済上の理由」3)で宝塚に進路を変えている。
夏代が入学した25期生は期待の若手が多く、萬代峯子、小雪京子、星影美砂子、大宮輝子(後の近江輝子)、若潮みつる、日高澄子、東風うらら、谷間小百合、聖瑞穂、沖ゆき子、朝霧照代、山鳩くるみ、帆影美里、鵲渡などがいた。多くが戦前に退団しているため、よほどの知識でないと現在では知られていない名前もあるが、うちの萬代、小雪、若潮、星影、山鳩、谷間については昭和13年末までに、歌劇団の機関誌である『歌劇』の表紙を飾っている。『歌劇』の表紙とはいわば歌劇団の「顔」であり、それを初舞台から3年以内にこれだけの生徒が選ばれているのは当時でも異例のことだった。いかに期待されていたかがわかるだろう。
その煌星揃う同期たちの中で、夏代は全く目立たない生徒だった。145cmと背が低く、娘役でも背が低い方だったが、地声がアルトで、劇団側からすると子供役でも使いにくい存在だった。持ち味の歌唱でも先輩が健在な上、同期も歌が得意な者がいて、チャンスもほとんど与えられなかった。
雑誌で同期同士の対談企画があっても夏代が出席することはなく、宝塚歌劇では戦前から多くのブロマイドが発売されているが、昭和20年(1945)までで夏代のものはわずか4種類しか確認できなかった。5年、6年目となってくると徐々に役は付いてくるが、その間、後輩にも役上で抜かれて、舞台の中心からはほど遠い存在であった。



折しも時代は戦争一色となり、宝塚歌劇もその影響は避けられず、生徒たちは公演と並行して病院などの慰問に回っていたが、昭和19年(1944)3月に宝塚大劇場と東京宝塚劇場が軍により閉鎖されると、歌劇団は自前の劇場を失い、いよいよ移動公演(農漁村、軍需施設などを回り慰問するための公演)中心の活動を余儀なくされた。
華々しい活躍をしていた同期たちは次々に退団していったが、夏代に最初の浮上の兆しが見えたのはこの時期であった。
毎日新聞社が主催していたクラシック音楽の登竜門「音楽コンクール」(注2)の声楽部門で二位に輝いたのである。二位といっても、一位は該当者がなく、参加者の中では最も高い評価であった。
コンクールには、歌劇団に許可を得ずに本名の多田玲子で出場していた。思いがけず入賞してしまい、責任を感じた夏代は名前が載った新聞を持って、歌劇団に辞意を伝えに行った。ところが歌劇団からは慰留を受けて、そのまま在籍することになる。
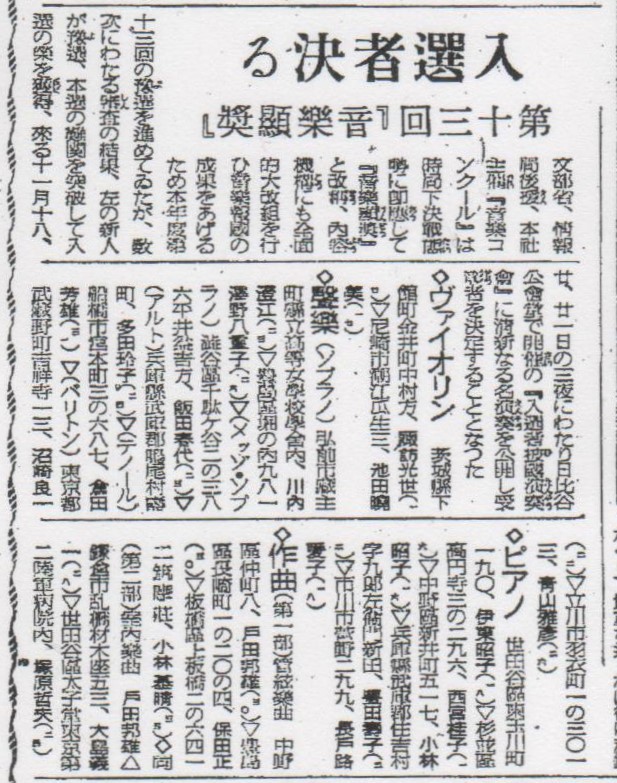
宝塚歌劇団は戦争中に多くの退団者を出して、昭和19年、20年は入学試験も行えなかった。また、昭和17年以降の入学者は学徒動員などで初舞台を踏めず、戦前に舞台経験のある者は約半数にまで減少してしまっていた。
その中で戦後、越路吹雪、乙羽信子、淡島千景、久慈あさみ、南悠子など、新世代のスターたちが次々に登場した。
夏代は返還された大劇場の初公演(注3)『カルメン』で、春日野八千代演じるホセの相手役としてカルメンを演じた。歴史的な公演で、戦前は主要な役を一回も経験していない夏代だから、まさしく大抜擢だった。
その後は、宝塚歌劇でも指折りの実力派歌手として活躍することになる。特に越路吹雪とのコンビは人気で、『ファイン・ロマンス』(昭和22年1月宝塚大劇場花組)『ミモザの花』(同12月宝塚中劇場花組)『ブギウギ巴里』(同24年2月宝塚大劇場花組)などで共演している。
当時の夏代はまだシャンソンへ関心を示してなく、越路と同じくジャズを歌う機会も多く、もともとの希望だったクラシックへの思いも捨てきれずにいた。

転機が訪れたのは昭和27年(1952)『シャンソン・ド・パリ』(宝塚大劇場6月雪組、7月花組、帝国劇場8-9月花組)である。フランスに外遊していた演出家の高木史朗が、そこで得た見聞をもとに構成したレビューである。日本では戦争によってシャンソンの新曲が断絶して、それは終戦後のこの時期もまだ続いていた。この作品はフランスで実際に聞いた新しいシャンソンを再び、日本へと紹介するものだった。
この頃、多くコンビを組んだ越路はすでに退団し、夏代も自らの進路に迷いが生じている時期だった。宝塚歌劇と同調するかのように、東宝系の劇場でもシャンソンを取り上げて、翌年昭和28年には戦前からのフランスの名歌手・ダミアが来日するなど、シャンソンが日本で広がる気運が高まっていった。ダミアのツアーには宝塚大劇場も含まれていて、夏代や生徒たちもその歌う姿を見ている。夏代はいても立ってもいられず、その前日の京都・公楽会館公演にも足を運んだ。
越路が退団したのが昭和25年、夏代の退団はその5年後の昭和30年で、その歌劇団の5年間は、夏代の生きる道がシャンソンへと決定づけられた時期とも言えよう。
気がつくと、終戦直後の宝塚をともに支えた越路吹雪、淡島千景、久慈あさみ、南悠子、乙羽信子たちのうち、夏代の他に残っているのは南のみであった。
夏代の宝塚での最終公演は『君の名は(ワルシャワの恋の物語)』(昭和29年宝塚大劇場 11月花組、12月星組)で、演出は菊田一夫であった。夏代は宝塚を辞める旨を菊田に打ち明けた。「辞めて、この後どうする気だ?」と尋ねる菊田に、夏代は「〈ジロー〉でシャンソンを歌います」と答えた。「ジロー」とは当時、神田に店を構えていたシャンソン喫茶の名前である。菊田は思わず「何も、すき好んでそんな苦労しなくても」と漏らした。宝塚、あるいは東宝系列に残っていれば、少なくても仕事に困ることはない。しかし決意は固かった。この時夏代は33歳であった。
シャンソン歌手として
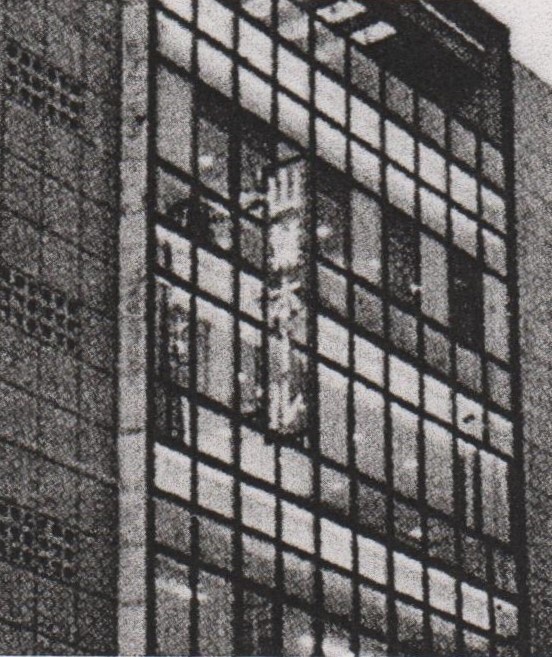
宝塚歌劇団退団から1年半ほどが過ぎた昭和31年5月、夏代は東京・山葉ホールにて、初めてのリサイタルを行う4)。第2回のリサイタルの日時は不明だが、第3回を昭和35年7月5)、第4回を昭和37年春頃6)と、順調に回数を重ねていく。この「リサイタル」の回数についてはプログラムや雑誌で本人や評論家が語っているもので、小規模やジョイントコンサートなど、その他公演については、もっと多くの舞台を踏んでいることを付け加えておく。
夏代が宝塚を飛び出した時期は、前述のようにちょうど「シャンソン・ブーム」のピークで、シャンソン喫茶で歌い、テレビやラジオでゲストとして呼ばれ、学校の講師もして(注4)、コンサート、小規模のリサイタルもあり、他の人気シャンソン歌手と同様に、忙しい日々を過ごした。
実力派歌手としての地位を固める一方で、昭和36年(1961)には初めてパリに足を運び、シャンソンの源流を自らの五感で確かめてきた。帰国後はシャンソン喫茶「ジロー」の一角で「深緑夏代の部屋」という空間を設け、歌手希望者やシャンソン関係者が集う場所を提供していた。この試みは5年に満たない期間で終わりを告げるが、後に渋谷にシャンソンバーを構えるなど、シャンソン指向者の集まる場所を作りたいという希望は、変わらず持ち続けたようである。その店にはシャンソン好きだった三島由紀夫も訪れたという。
夏代がシャンソン界に与えた影響を考える時、その講師活動を外すことはできない。昭和41年から52年に至る約11年間、古巣の宝塚歌劇団で生徒にシャンソンを教えた。教え子には、真帆しぶき、笹潤子、安奈淳、鳳蘭、大原ますみ、萬あきら、星奈佐和子などがいる(注5)。
昭和55年(1980)からは毎日新聞の依頼を受けて、朝日カルチャーセンターでシャンソン教室を受け持つことになる7)。宝塚の生徒以外でも、歌手やその志望者相手にレッスンをすることはあったが、カルチャーセンターの生徒の多くは一般の主婦などで、シャンソンの新しい裾野を広げることに貢献した。
正確な人数を把握することは難しいが、本人はレッスンした人数を「1万人以上」と語っている8)9)。比較することもまた困難だが、シャンソンだけでなく日本の音楽史上全体に広げても突出した数字ではないだろうか。
歌手活動では、平成4年度(1992・第47回)芸術祭賞を「深緑夏代―歌・この不思議なるもの―」の歌唱が評価を受けて受賞10)、平成六年には勲四等瑞宝章を授章した11)。しかし平成10年(1998)夏に吐血し入院、その時は胃潰瘍と診断されて退院するが、後に胃癌が判明する。
翌年1月に胃癌摘出術が行われ12)、復帰も危ぶまれたが徐々に回復して、ステージに復帰する。その後、平成21年1月に体調を崩し同年8月に逝去するまで現役歌手であり続けた。最後のステージは平成21年1月5日、教え子の矢田部道一が創業したシャンソニエ、新宿シャンパーニュであった。享年87歳。晩年は「現役最年長歌手」と冠されることもあった。
日本シャンソンと深緑夏代

ここまで夏代の歌手人生について概略を述べてきたが、あらためて日本シャンソンにおける彼女の評価について考えてみたい。
夏代がシャンソン歌手としてデビューした当時、雑誌ではシャンソン歌手の人気投票が行われていた。夏代は国内でそれぞれ7位、11位にランクインしている13)。芦野宏、越路吹雪、中原美紗緖、高英男、淡谷のり子、ビショップ節子はいずれも夏代より上位にランキングされている。
年末の風物詩とされる「紅白歌合戦」に芦野10回、越路15回、中原7回、高7回、淡谷9回と出演している1)が、夏代は一度もその機会はなかった。紅白だけで歌手の評価を計ることは難しいが、大衆的な人気という面では、人気投票の結果と同様に上記の歌手よりも一歩下がった位置にいたのではないかと考えられる。
彼女の日本シャンソン界における評価について、文化プロデューサー、演劇評論家の河内厚郎氏に尋ねた。氏は年少時代からシャンソンファンで、若い頃には自身で歌手として活動していたこともある。またKCAシャンソンコンクール審査委員長も務めている。
〈それだけの実力がありながら、人気という面では他の歌手たちに後塵を拝していた理由は何かあるのでしょうか?〉
河内 彼女は実力では一番、音楽的な教養も高いし、ある意味では他の歌手の持っている際立った個性という点については乏しかったかもしれない。大衆受けする個性がないと世間的な人気はなかなか上がってこないと思う。
昭和30年代、フランスの歌手に日本語詞を歌わせて、国内でレコードとして販売するという試みが行われていた。ブームだからこそ需要もあったわけだが、その際にレコード会社は夏代に日本語の見本となる吹き込みを依頼している。彼女の歌唱が基本に忠実で質の高いものであったからだろう。
そのいわばフランスの歌手にも見本となるような「正統派の」あるいは良い意味で「教科書的な」性質が、あるいは大衆的人気を得るのに不向きであったのかもしれない。
風さやかさんは宝塚歌劇団49期生で、夏代のレッスンも受けたことがある。実際に接した印象など伺いたいと申し出た時、当初は「他にも繋がりの深いお弟子さんがたくさんいますから」と固辞されていたが、お願いして談話をいただいた。
〈一般的な人気という面では、他の歌手の方に比べて不遇だった面もあるように思うのですが、それについてはいかがですか?〉
風 あまりマネージメント的なことに頓着していませんでしたからね… 先生はね、それは相当口惜しい思いもしたと思いますよ。でも、自分の歌に誇りを持っていましたから、堅実にご自身の道を歩まれたのだと思います。
夏代が宝塚におけるシャンソンの幹を作った一人であることは間違いがない。
岸田辰彌、白井鐵造、高木史朗といった演出家が日本にシャンソンを導き、夏代は歌手として歌い、次代へとつなぐ橋渡しをしてきた。講師としての業績はどのシャンソン歌手よりも優れているが、彼女の本質は本人が望んだように「一人の歌手」だと思う。誰よりも歌うことが好きだったのだ。
彼女が芸能活動をスタートした宝塚歌劇は今年、110周年を迎えた。
平成18年(2006)より、宝塚市内に在住する演奏家や音楽愛好家などが「宝塚シャンソン化計画」という市民団体を作り、宝塚市や宝塚市文化財団などの公演のもと、イベントや啓蒙活動を実施している。
昭和2年(1927)に宝塚少女歌劇が『モン・パリ』を上演して、3年後の令和9年には100年を迎える。『モン・パリ』を日本シャンソンの始まりとして、100周年に向けて阪神各都市を主たる舞台に、これまでの歴史や変遷を振り返り、未来に向けて繫いでいこうという取り組みが見られる。団体は「日本シャンソン100年記念事業実行委員会」と名付けられ、今年(令和6年)4月に結成された。
9月1日にはその「第一回記念シンポジウム&コンサート」が開催される。
夏代が逝去したのが2009年8月31日で今年は15周忌に当たる。その命日の翌日に日本シャンソンの新たな船出が企画されているのも奇縁と言えるかもしれない。

宝塚を日本シャンソンの源流とするならば、その宝塚で生徒を教え続けてその伝統を繫いできた夏代もまた、日本シャンソンの大切な紡ぎ手であったといえる。夏代は、愛するシャンソンが宝塚に満ちるのが何より楽しみに違いない。どこかから眺めて、生前と同じきっぷの良い笑みを浮かべていることだろう。
注釈
1 昭和15年(1940)に宝塚少女歌劇(団)から宝塚歌劇(団)に名称変更。
2 現在の「日本音楽コンクール」。昭和19年は外国語が使えなかったため「音楽顕彰」という名称が使われた。当年は予選と入賞者発表会も含めると9月~11月にかけて実施された。
3 宝塚大劇場は、昭和19年3月以降は海軍、終戦後は進駐軍が接収していた。大劇場返還後の初公演は、昭和21年4月22日~5月30日に雪組が『カルメン』と『春のをどり』を演じている。
4 ごく短い期間であるが、「スクール」や「学院」という名前を持つ養成所的施設がブーム時には複数存在した。夏代は、高木東六が院長を務めた「東京エコール・ド・シャンソン(東京シャンソン学院)」の講師として、名前を連ねていた(雑誌『シャンソン』の誌内広告にて)。
5 教え子については膨大な人数に上がり、列挙の基準が難しいため、ここでは2010年に夏代の追悼公演に参加した生徒たちから抜粋した。
引用文献
※ タイトル名をクリックすると、該当ページ、あるいはAmazonの商品ページに移動します。
1)生明俊雄「シャンソンと日本人」集英社新書.2023
2)芦野宏「幸福を売る男 私のシャンソン史」日本放送出版協会.1998
3)「私も映画に入りたいわ 狙われる宝塚と松竹の歌姫たち」(『週刊娯楽よみうり』昭和30年11月11日号P10-15)
4)伊東哲夫「深緑夏代シャンソン・リサイタル」(『音楽の友』昭和31年8月号P200)
5)永野一郎「リサイタルから 深緑夏代リサイタル」(『シャンソン』昭和35年8月号P14)
6)「1962深緑夏代・シャンソンリサイタル」公演プログラム ※月日の記載がなし
7)下瀬直子『深緑夏代 宝塚・シャンソンに生きる』彩流社.2007
8)「日本で最初に「枯葉」を歌ったのは私です 84歳の現役シャンソン歌手は伝説のタカラジェンヌ」(『婦人公論』2006年6月7日号)
9)「人生悠々/宝塚娘役からシャンソン歌手へ 歌に魅せられて七十余年 深緑夏代さん85歳」(『毎日が発見』2006年6月号)
10)文化庁ホームページ より。2024年7月31日閲覧
11)日本シャンソン協会ホームページ より。2024年7月31日閲覧
12)「私の養生学 深緑夏代さん 八〇歳のシャンソン歌手 胃がんを乗り越え、昨年コンサート活動に復帰〈シャンソンは私の生きる道〉」(『ミマン』2002年7月号)
13)『シャンソン』昭和33年5月号、同34年1月号









コメントを残す